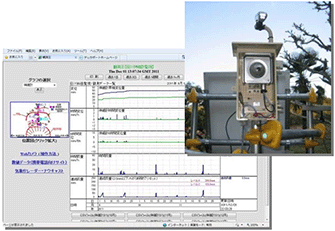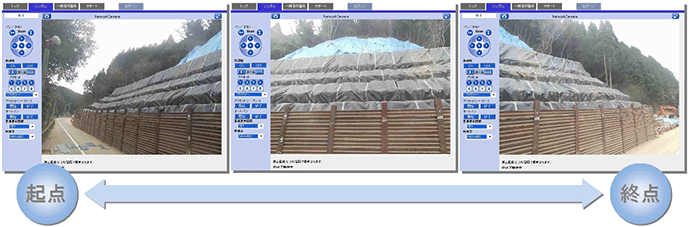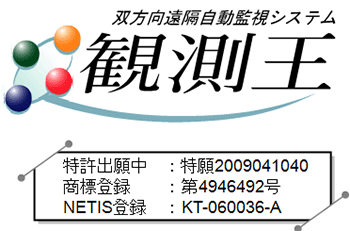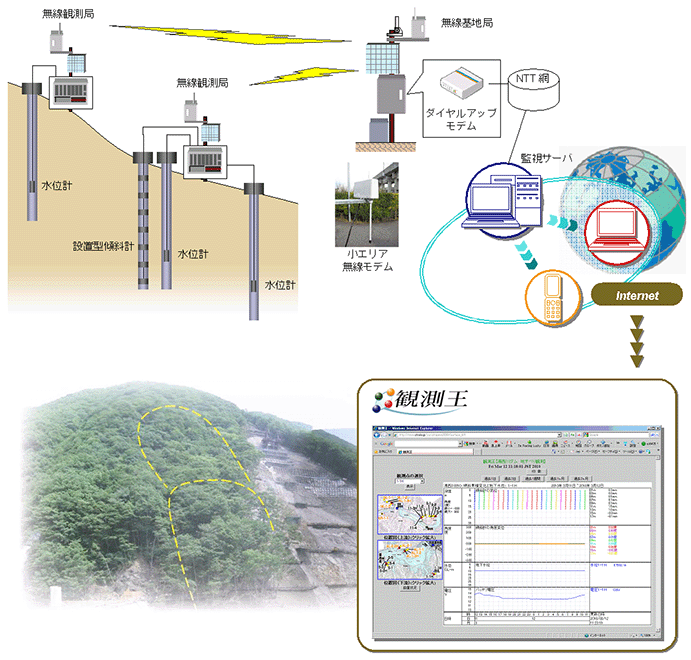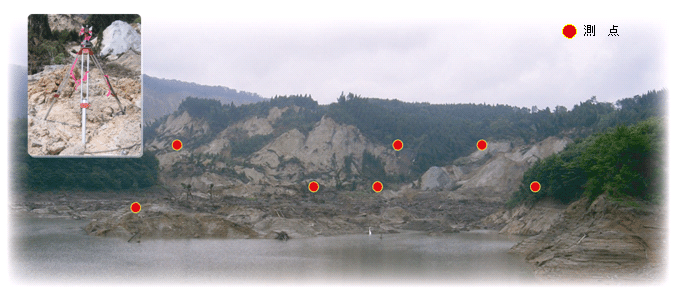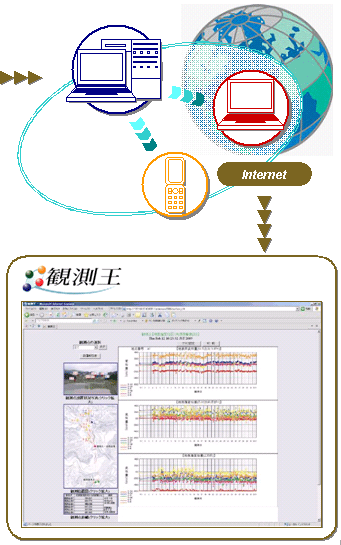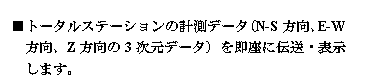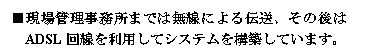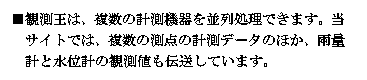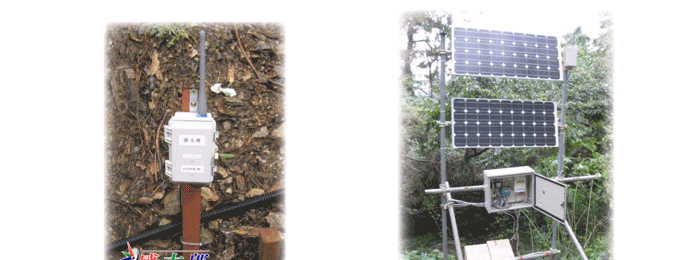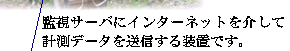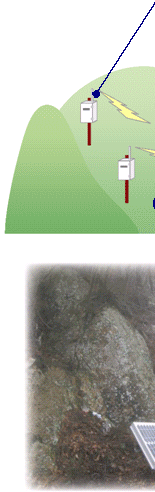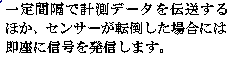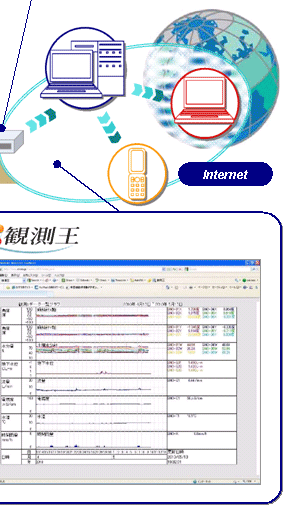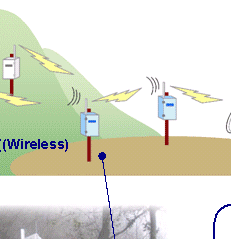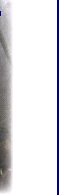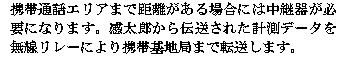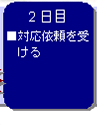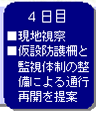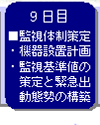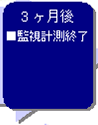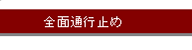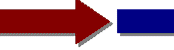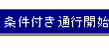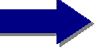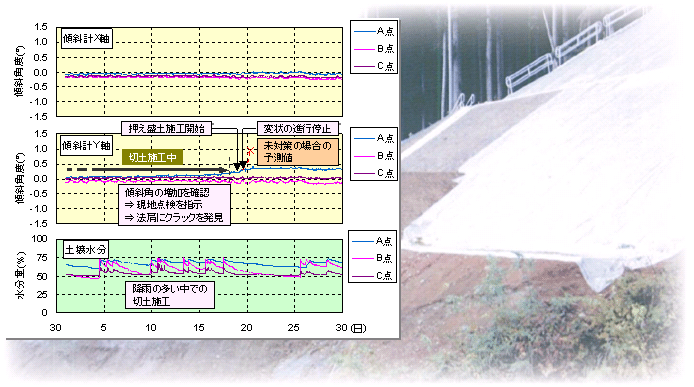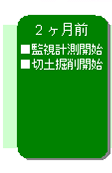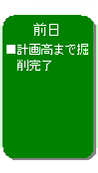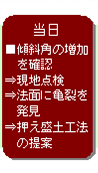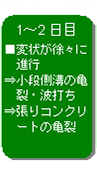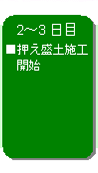■ 問い合わせ先
■技術サポート
防災モニタリング事業部 担当:山口・後藤・田邊
〒169-8612 東京都新宿区西早稲田3-13-5 Tel 03-6228-0326 Fax 03-3208-3572

|
|
|
機器の設置と自動観測システムの構築を行います。通信回線の申請など煩わしい手続きも弊社が代行します。
商用電源が無い場所では、ソーラーパネルとバッテリーによって稼働させます。その他、警告灯や警報用スピーカーの設置などについてもご相談ください。
|
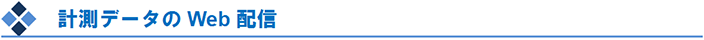
|
|
計測データはサーバでグラフ化し、インターネットを通じてユーザに配信します。汎用ブラウザで閲覧が可能であり、IDとパスワードによってセキュリティを確保します。
なお、サーバは弊社所有※のものをご利用いただけます。ユーザ側でのサーバ導入、設置スペースの確保は不要です。
|
|

|
|
|
あらかじめ設定した管理基準値を超過すると、警報メールを自動配信します。管理基準値は、警報レベルに応じて複数設定することができます。
管理基準値の設定や警報レベルの区分についても、弊社がサポート致します。
|

|
|
リアルタイムデータを常時監視し、緊急事態に備えます。管理基準値とは別に、刻々と変動するデータの状況に着目し、異常を察知した場合は即刻現場へ連絡します。
下図のイメージで計測データを評価しています。
|
|
|
|

|
|
異常を察知、または管理基準値を超過した場合には、現地に急行し、状況を把握します。
また、計測機器の破損など、システム稼働状況を確認します。
|
※ 弊社は、不測の事態に備えて、K3-System専用サーバを国内2カ所に設置しています。
|
観測王 〜双方向遠隔自動監視システム〜
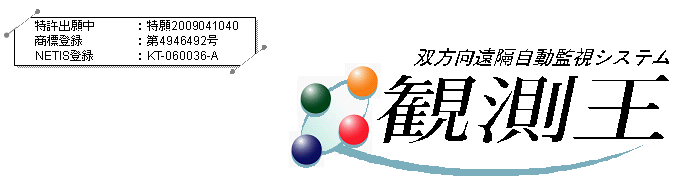
「観測王」は、現地の計測機器から自動的に伝送されるデータを弊社のサーバ上でグラフ化し、インターネットを介して配信するとともに、現地計測機器を遠隔地から制御することができるシステム(双方向の監視・制御)であり、弊社がご提案する計測・監視・警戒サービス「K3-System」のベースとなるシステムです。
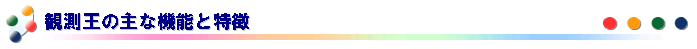
観測王の特徴 |
導入効果 |
観測局と監視局の双方向通信
(観測局:データ配信、監視局:機器制御) |
■観測の省力化・低コスト化を実現します。
■現地立入作業を最小限に抑えます。 |
監視局PCから現地のロガーを直接制御 |
■現地基地局に、制御用のPCを置く必要はありません。
■システム全体の稼働率向上につながります。 |
リアルタイムデータ配信と常時監視 |
■異常事態の早期発見につながります。
■自動メールによる警報発信が可能です。
■機器異常の早期発見によって欠測期間を最小化します |
Webブラウザによるデータ閲覧※1 |
■専用端末(ソフト・ハード)は不要です。
■PC・携帯電話があればいつでもどこでも閲覧できます※2。 |
様々な計測機器との接続実績※3 |
■既設計測機器を継続利用できます。
■手動・半自動観測を自動観測に切り替えることも可能です。
■雨量計・トータルステーション・Webカメラ等との接続実績もございます。
|
自社サーバの保有と利用提供(有償) |
■サーバ設置スペース、導入費用は不要です。
■サーバの管理・メンテナンスも弊社が行います。
■サーバは二重化(国内2ヶ所に設置)しています。 |
■接続イメージ図
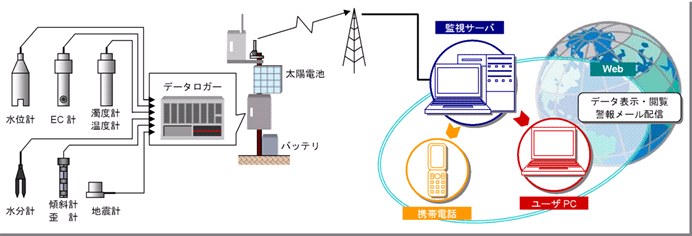

|
急傾斜地や地すべり、造成地の地盤変位の計測の他、気象、水文・水質など、各種の計測機器と組み合わせることで、土砂災害危険個所の監視、土留め・掘削などの施工中の安全管理、既設構造物の維持管理など、多用途にご利用いただけます。
また、通信部分は有線・無線、一般回線・携帯電話回線・インターネット回線(光回線、ADSL等)を自由に選択することができます※4。
|
主な接続可能機器
種別 |
計測機器 |
地盤変位 |
■伸縮計 ■傾斜センサー
■パイプ歪計 ■固定式孔内傾斜計
■継目計
|
水文 |
■転倒ます型雨量計 ■水圧式水位計
■差込式土壌水分計
|
水質 |
■pH計 ■電気伝導度計
■濁度計 ■ORP計
■水温計
|
その他 |
■Webカメラ
■トータルステーション
|
|
|
|

|
|
観測データの閲覧には汎用ブラウザを使用します。ブラウザ画面は、観測目的やお客様の要望に応じてカスタマイズすることができます。また、あらかじめ設定した基準値を超過した際には、監視サーバから自動的に警報メールを発信します。
|
|
|
※1 観測データの閲覧にはIDとパスワードが必要になります。閲覧用サイト構築後、閲覧先URL、ID及びパスワードをお客様にメールで配信します。
※2 閲覧用サイト(携帯版)では、グラフ表示および画像データの閲覧はできません。
※3 計測機器の接続可否については、技術サポート窓口にご相談ください。
※4 現地と弊社サーバ間の伝送は、携帯電話回線、インターネット専用回線等を使用します。通信事業者の事由による伝送の遅れや欠損については、弊社では保証し兼ねます。
|
▲ページのトップへ
感太郎 〜斜面崩壊感知センサー〜

自然および人工斜面は,緩みやすべり等を要因として、徐々に変動していきます。「感太郎」は,この変動を捉えることを目的として開発された傾斜センサーです。
計測部にはMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術を活用し,通信制御部には特定小電力無線を採用したことで,小型化・軽量化、省電力、そして低価格を実現しました。これにより、従来の観測機器と比較して、設置の簡素化と多点化が可能になりました。また,双方向遠隔自動監視システム「観測王」との組み合わせによって、斜面災害に対する迅速な情報提供を可能にします。
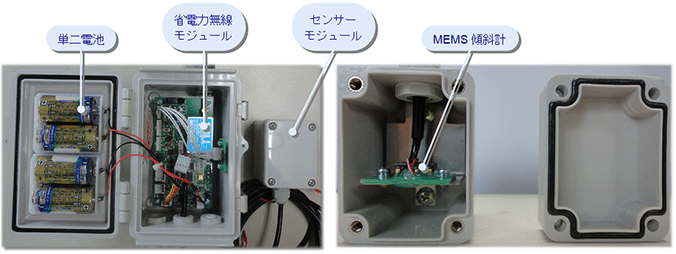
|
仕様:斜面崩壊感知センサー【感太郎】
|
センサーユニット
|
|
■二軸傾斜計モジュール(−30°〜+30°)
■三軸傾斜計モジュール(−90°〜+90°)
■転倒検知(±30°傾いたとき)
|
|
土壌水分計(オプション)
|
|
■簡易型土壌水分計EC5-5
■測定精度:±3%
|
|
通 信
|
|
■無線適合規格:ARIB STD-T67適合
■送受信周波数:429.2500〜429.7375MHz
■伝送可能距離:約600m(無障害時)
|
|
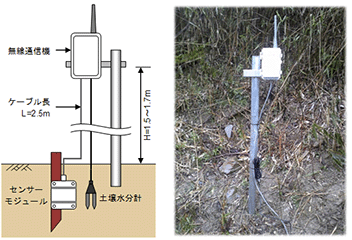
|

|
◆地盤の傾斜角を計測する「感太郎」
斜面の変位(地盤変動)により、斜面の地盤は右図のように傾動します。それに伴って斜面地盤に打ち込んだ杭(L型アングル)と、これに結束した傾斜センサーが傾きます。この傾斜角(θ)を時系列で計測します。
これによって、斜面の変位状況とそのスピードを把握し、斜面の危険度を評価します。
|
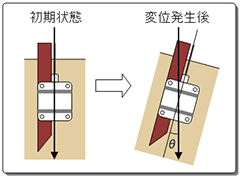
|
|
|
|
◆独自の強みを有する「感太郎」
地すべりや斜面の変位計測には、伸縮計がよく用いられます。伸縮計は、長年の実績を有する計測機器であるとともに、注意・警戒・避難の目安となる閾値も有する実用性の高い計測機器と言えます。しかしながら、1.移動土塊と不動土塊の境界が不明確な場合には不向き、2.設置スペース(平均1m×10m) を要する、3.設置に時間が掛かるといった問題もあります。
一方、「感太郎」は、1.省スペースかつ低価格のため多数設置できる、2.無線通信により設置場所の自由度を確保できる、3.設置の手間が少ないといった長所があります。
災害直後の残存土塊の状況把握など、計測目的や現地の状況によって、「感太郎」が有利な場合があります。また、「感太郎」と伸縮計など他の計測機器とを互いの短所を補い合うように組み合わせることで、計測目的を達成するだけでなく。互いのデータをクロスチェックできるといった効果も得られます。
|

|
|
「感太郎」は、斜面表層の土砂部に杭(L型アングル)とともに埋込むことを基本としていますが、治具を工夫して、不安定な岩塊(転石)の監視や土留壁(SMW)の変状計測に活用した事例があります。
|
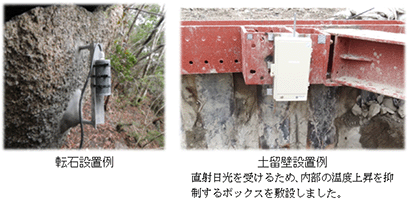
|
▲ページのトップへ
K太 〜簡易型多段式地中傾斜計〜
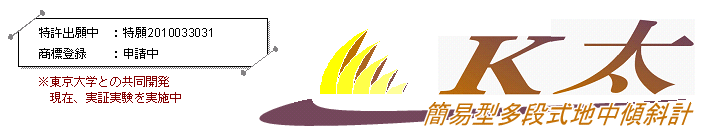
従来の斜面表層の監視に対して、地中深くの土砂挙動を監視する簡易型多段式地中傾斜計(商品名:「K太」)を開発しました。土砂災害復旧作業中の二次災害防止などを目的として、少人数で短時間に設置できる構造としています。「観測王」と組み合わせて、斜面の自動監視システムを迅速に構築することが可能です。
■K太 イメージ図
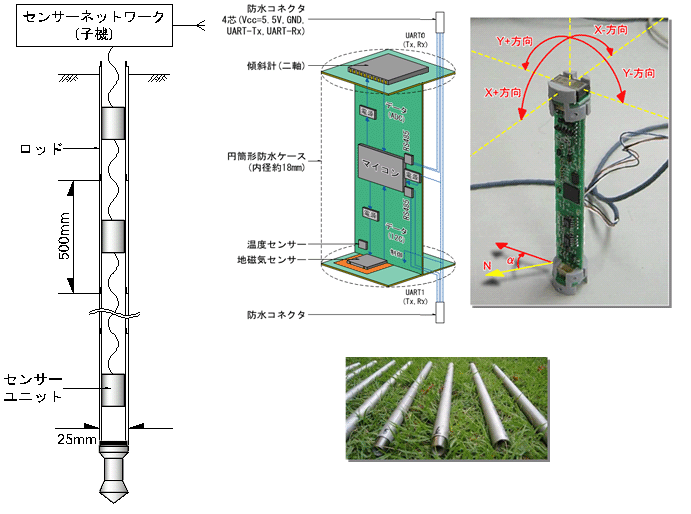
簡易型多段式地中傾斜計【K太】の特徴
 直径25mmのロッド内部にセンサーユニットを組み込み
直径25mmのロッド内部にセンサーユニットを組み込み
 小型傾斜計(二軸)を鉛直方向に等間隔で設置し、斜面の微小な変位を計測
小型傾斜計(二軸)を鉛直方向に等間隔で設置し、斜面の微小な変位を計測
 地磁気センサーにより地盤内のセンサーユニットの向きを測定
地磁気センサーにより地盤内のセンサーユニットの向きを測定
 ロッドは500mm/本、必要な深さまで継ぎ足しながら貫入
ロッドは500mm/本、必要な深さまで継ぎ足しながら貫入
 設置は簡易動的コーン貫入試験の要領(少人数・短時間で設置可能)
設置は簡易動的コーン貫入試験の要領(少人数・短時間で設置可能)
 地上部のセンサーネットワーク(特定省電力無線)によりデータを回収
地上部のセンサーネットワーク(特定省電力無線)によりデータを回収
 センサーユニット及びセンサーネットワーク(子機)はアルカリ乾電池または小型太陽電池で稼動
センサーユニット及びセンサーネットワーク(子機)はアルカリ乾電池または小型太陽電池で稼動
▲ページのトップへ
遠隔監視カメラ
計測データだけでは、遠隔地の現場の様子を正確に把握することはできません。
精度の高い計測システムを構築しても、
自分の目で見ないと不安が解消されない・・・
いち早く現場の様子を知りたい・・・
そんな要望にお応えするツールです。

|
インターネットを介して、遠隔地から現地のカメラを制御します。パン&チルト、ズームはもちろんのこと、カメラのON/OFF、画像更新速度の変更(1s間隔〜)などが可能です※1。
各種計測機器との併用によって、よりリアルな現地観測をご提供します。
|
|
|
|
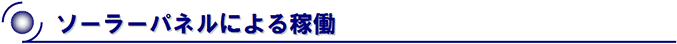
|
通常、WebカメラはOFF状態にしておき、必要なときに遠隔操作で起動します。また、一定時間経過すると、自動的にOFFにします。これによって、電力消費を抑制しました。
電力消費の抑制によって、ソーラーパネルとバッテリーによる稼働を実現しました。したがって、山間部など商用電源のない場所でもご利用いただけます。
|
|

機器の構成例を下図に示します※2。
弊社は、設置目的及び現地条件に応じて、機器の選定や配置計画など、最適な構成をご提案致します。技術サポート窓口までお気軽にご相談ください。
|
本サービスは、弊社の双方向遠隔自動監視システム「観測王」(NETIS登録:KT-060036-A) をベースに構築しています。
「観測王」では、計測データやカメラ画像をWebブラウザによって閲覧します※3。したがって、新たに専用のソフト及びハードを導入する必要はありません。また、弊社が保有するサーバをご利用いただければ、サーバの設置スペースや導入費用も掛かりません※4。
|
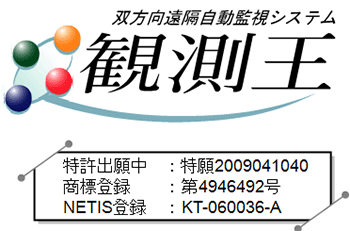
|
※1 Webカメラは、Panasonic製ネットワークカメラ(BB-HCM735)を標準としています。その他のカメラの使用にあたっては、技術サポートにご相談下さい。
※2 現地と弊社サーバ間の伝送は、携帯電話回線、インターネット専用回線等を使用します。通信事業者の事由による伝送の遅れや欠損については、弊社では保証し兼ねます。
※3 カメラ画像の閲覧にはIDとパスワードが必要になります。閲覧用サイト構築後、閲覧先URL、ID及びパスワードをお客様にメールで配信します。
※4 サーバ利用は有償です。
|
▲ページのトップへ
観測王・感太郎・K太の事例集

ダム貯水池周辺の地すべり自動観測(平成20〜21年度)
ダム貯水池周辺の地すべりブロックにおいて、湛水時の地すべり挙動及び地下水位変動を把握するため、設置型傾斜計、孔内水位計を設置しました。設置型傾斜計と孔内水位計のデータを「観測王」によってリアルタイムWeb配信し、変状の常時監視を実施しています。弊社は、地すべり調査・解析・動態観測などの豊富な実績をベースに計測機器の選定、配置計画から自動観測システムの構築までサポート致します。
■イメージ図
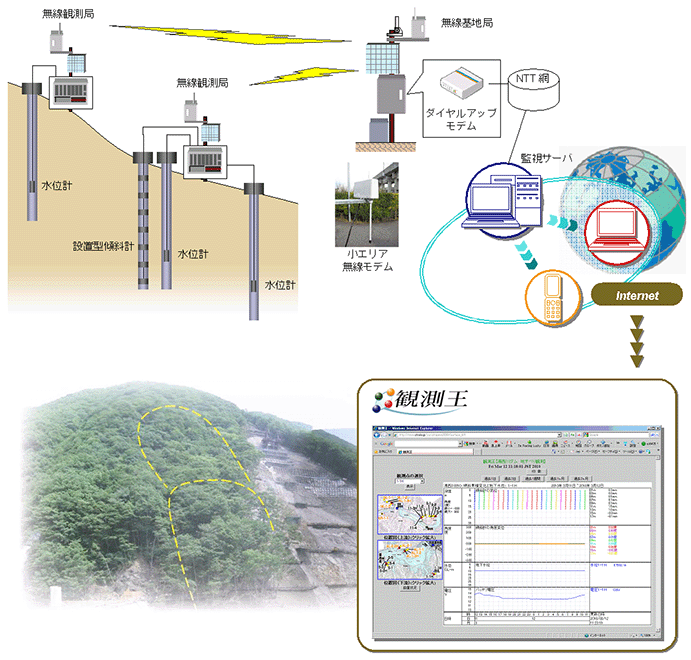
■当該ダム周辺では、設置型傾斜計86基、孔内水位計15基の自動観測を実施しています。
■無線観測局から無線基地局までは、小エリア無線を使用しています。小エリア無線の他に特定小電力無線を使用することができます。現地の状況に応じて、無線方式、あるいは有線・無線を使い分け、計測の確実性、トータルコストの観点から、最適な方法をご提案します。
■無線基地局からはNTT公衆回線を使用していますが、これも現地の通信条件に応じて、ADSL回線、光回線、携帯電話(FOMA通信)などに対応します。
▲ページのトップへ

トータルステーションによる地すべり土塊のモニタリング
(平成20年度)
地震を誘因として発生した大規模な地すべりの現場で、地すべり土塊のその後の挙動を「観測王」に接続したトータルステーションによってモニタリングしています。「観測王」は、様々な計測センサーを接続した実績があります。現地の状況、目的に応じた計測センサーを選定し、常時監視とリアルタイムWeb配信を実現します。
■イメージ図
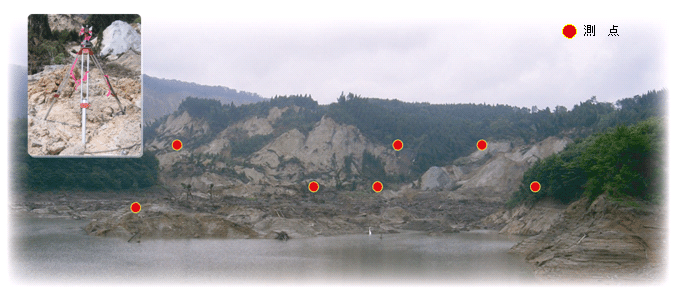
▲ページのトップへ
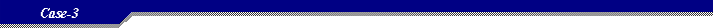
「観測王」・「感太郎」による斜面の常時監視(平成21年度)
急傾斜地などの土砂災害危険箇所に斜面崩壊感知センサー「感太郎」を設置し、「観測王」を用いて現地状況の自動監視を実施しています。斜面の変状を即座にキャッチすることはもちろん、遠隔地からのデータサンプリング間隔の変更、メモリカード内のデータ回収などの計測機器制御によって省力化・低コスト化を実現します。
■イメージ図
▲ページのトップへ

斜面監視〜災害発生から復旧工事着工まで〜(平成22年度)
道路沿い斜面で崩壊等の災害が発生すると、道路を塞いだ土砂を取り除いても、斜面は地山が剥き出しとなっているため、復旧工事が完了するまでは二次災害が生じやすい危険な状態にあります。一方で,地域動脈として車両通行も求められるため、本復旧までの仮通行期間は非常に高度な管理が必要になります。弊社では、計測機器による監視とデータのリアルタイムWeb配信、警報メール発信、24時間監視、技術者による斜面点検・・・等の総合的な斜面監視サービスにより、災害時の道路管理をサポート致します。
■イメージ図
■Q&A
設置機器 |
Q:設置した計測機器は? データ取得間隔は?
A:斜面崩壊感知センサー(弊社製:感太郎)と雨量計を設置しました。データサンプリング間隔は10分としました。
|
設置位置 |
Q:設置した位置は?
A:崩壊斜面中段に残る不安定な土塊と頂部の未崩落土塊に設置しました。
|
警報基準 |
Q:警報メール発信の段階区分は?
A:「出動準備・待機」、「通行止め準備」、「通行止め」の3段階としました。
|
適用基準 |
Q:警報メール発信に用いた基準は?
A:当該県道の雨量規制基準と伸縮計基準の傾斜換算値を用いました。ただし、通常より危険な状態にあることを考慮し、計測当初は1ランク厳しい基準を適用しました。その後、現地状況に応じて徐々に適用基準を下げました。
|
現地点検 |
Q:現地点検の実施時期は?
A:警報メール発信の度に実施しました。このデータを蓄積して、基準値の見直しを行いました。
|
▲ページのトップへ

施工監視〜切土法面施工に伴う安全監視〜(平成22年度)
切土法面は事前調査において把握した地山の硬軟・風化程度・地質構造・地下水状況等を基に、掘削勾配や対策工が設計されています。
しかし、調査で把握しきれない風化や地質構造の部分的な相違が原因で、法面が変状し、果ては崩壊に至ることが多々あります。したがって、切土施工においては変状の程度が小さい段階でいち早くこれをキャッチし、応急処置を行うことが必要になります。
弊社は、フレキシブルな計測機器の配置と測定、遠隔自動監視等の総合的な施工監視サービスにより、安全で経済的な安全管理をサポート致します。
■イメージ図
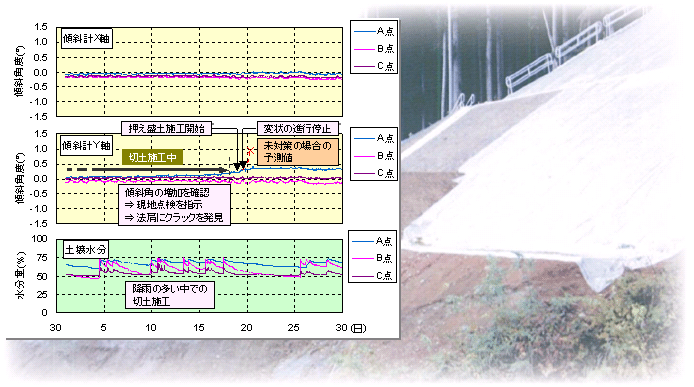
■Q&A
設置機器 |
Q:設置した計測機器は? データ取得間隔は?
A:斜面崩壊感知センサー(弊社製:感太郎)を設置しました。データサンプリング間隔は10分としました。
|
警報基準 |
Q:警報基準は設定したか?
A:設定しました。ただし、事例に示した変状は基準値未満でしたが、データ監視をしていた係員が不審に思い、現地に緊急連絡することで発見できました。
|
自動監視の必要性 |
Q:定期的な巡視・点検を行えば、自動監視システムは不要では?
A:定期点検で亀裂を発見できたとしても、どうしても発生から発見までの間にタイムラグが発生してしまいます。本事例では、データ監視を受けて、定期点検よりも詳細な緊急点検を行い、わずかな亀裂を早期に発見することができました。また、観測機器を用いることで、人間では認識できないレベルのわずかな変状でも検知することができます。
|
▲ページのトップへ
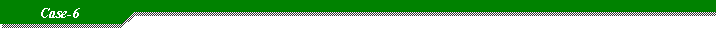
基礎杭施工に伴う近傍商用井戸の水質監視(平成21年度)
構造物基礎の施工が帯水層に達する場合、その帯水層から取水している近傍井戸の水質への影響が懸念されます。特に、商用井戸の場合は、デリケートな管理と非常時対応が求められます。
弊社は、「土」と「水」のエキスパートとして、リアルタイム監視サービスをはじめ、観測孔の配置計画、管理基準値の設定、緊急対応マニュアルの策定等、総合的に地下水の水質監視をサポート致します。
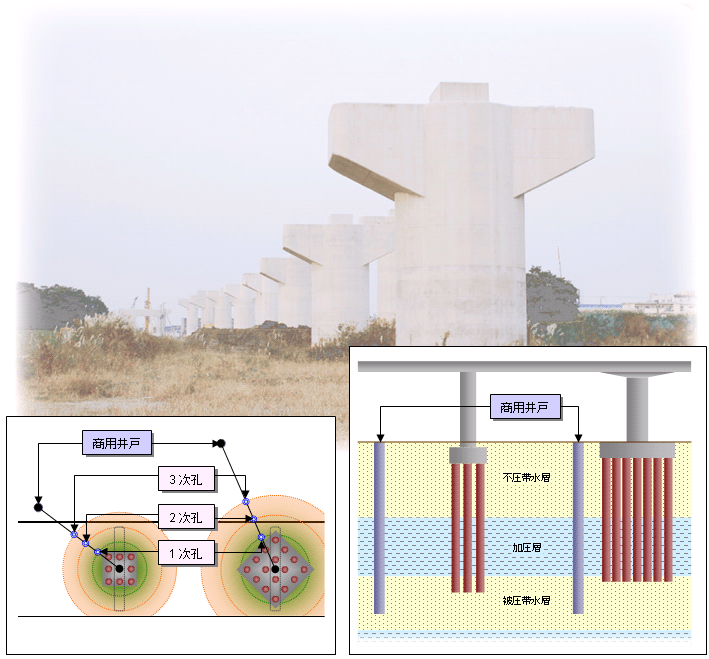
■Q&A
観測孔設置 |
Q:設置した観測機器は?観測孔の配置は?
A:施工箇所に近い順に1次孔、2次孔、3次孔を配置し、濁度計を設置しました。
|
警報基準 |
Q:警報メール発信の段階区分は?
A:「正常」,「注意」,「警戒」の3段階としました。3次孔には最も厳しい基準値を設定しました。
|
データ間隔 |
Q:データサンプリング間隔は?
A:「正常」時は5分間隔、「注意」・「警戒」時は1分間隔としました。なお、データサンプリング間隔は遠隔操作で変更することができます。
|
緊急対応 |
Q:警戒に達したときは?
A:杭が被圧帯水層に達した際に3次孔が「警戒」レベルとなり、施工を一端中断しました。その後、平常時の値に戻ったことを確認した後、施工を再開しました。施工再開にあたっては、水質を維持するため、掘進速度を当初より小さくしました。
|
▲ページのトップへ
■ 問い合わせ先
■技術サポート
防災モニタリング事業部 担当:山口・後藤・田邊
〒169-8612 東京都新宿区西早稲田3-13-5 Tel 03-6228-0326 Fax 03-3208-3572
どんな疑問点・ご相談でも構いません! 私たちに、お気軽に、お問い合わせ下さい!!
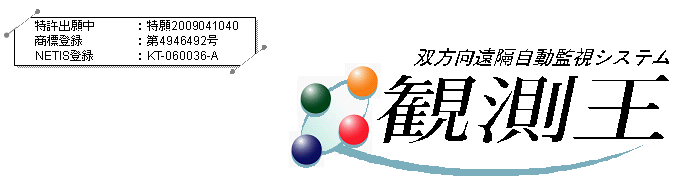
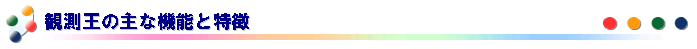
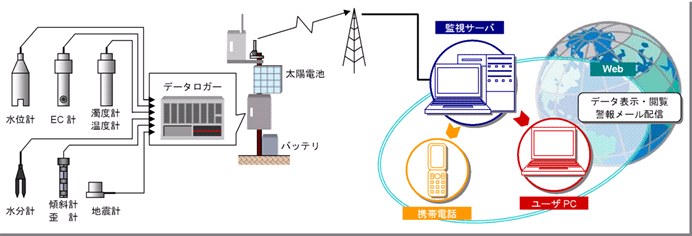

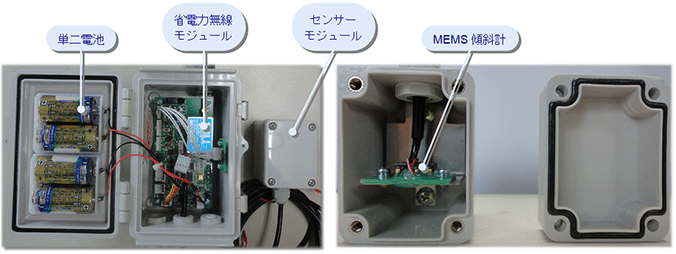
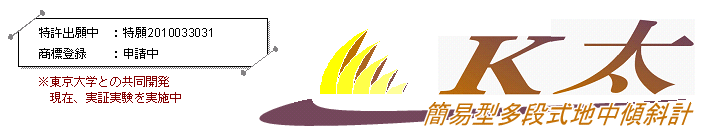
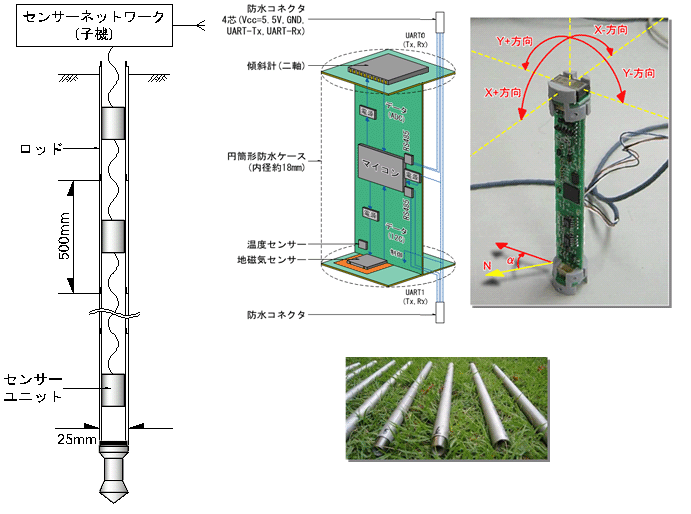
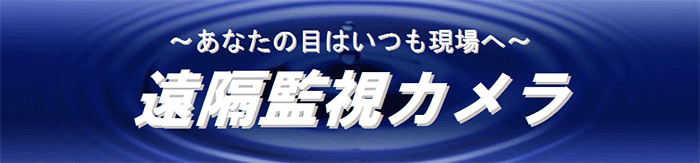

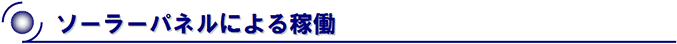

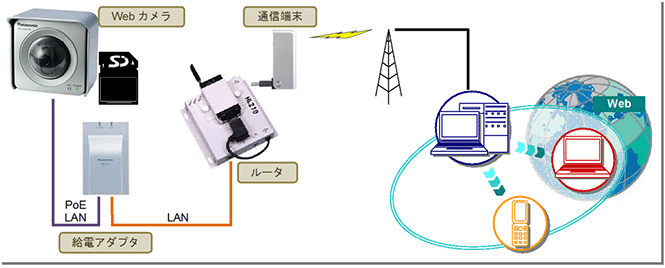


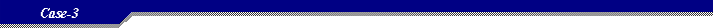

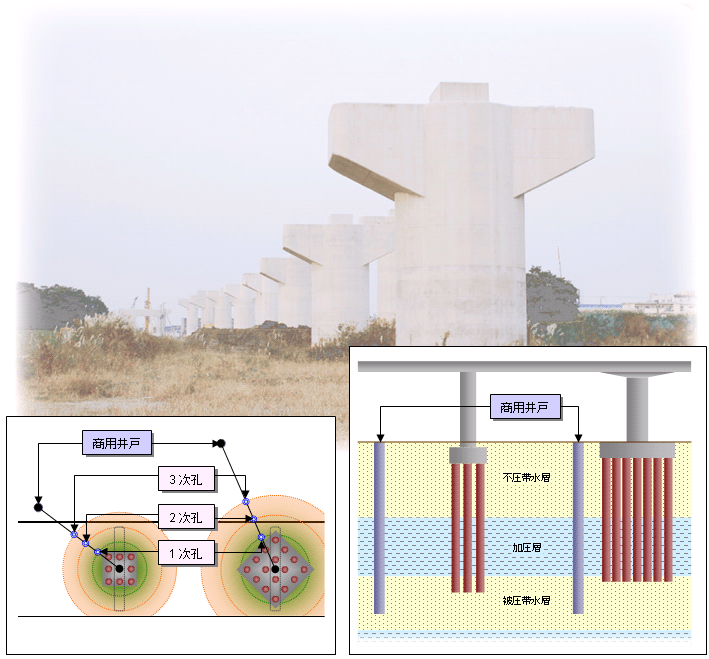

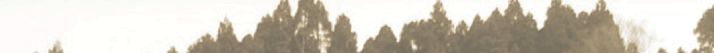

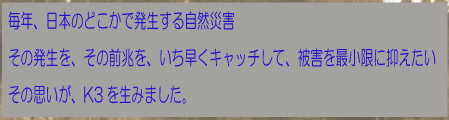









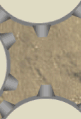
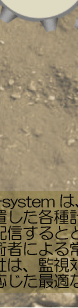
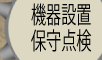
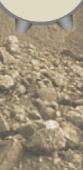
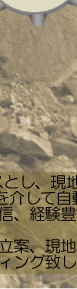
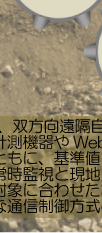

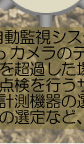


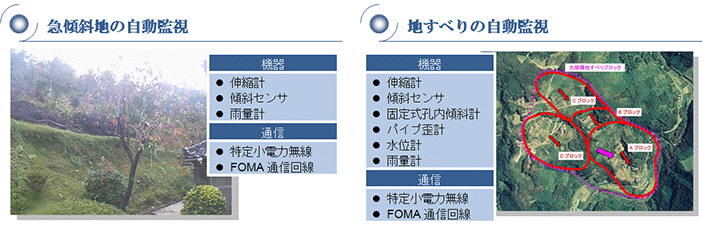
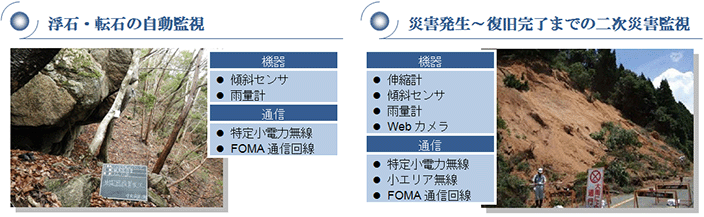
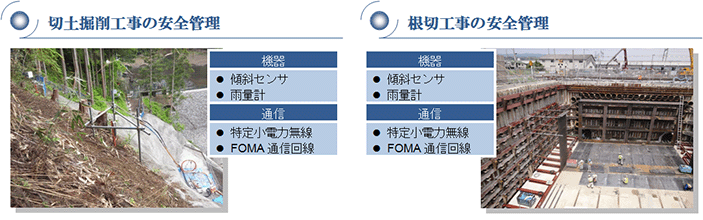
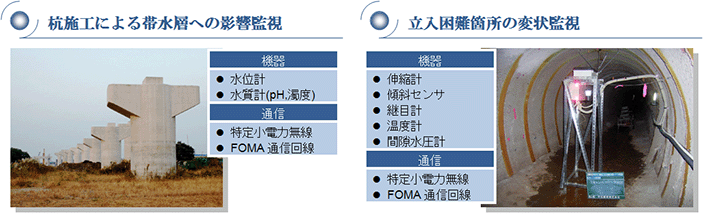

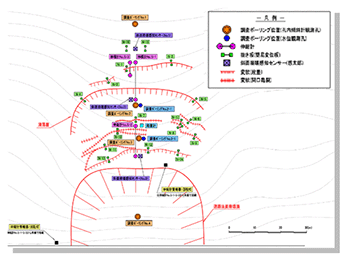
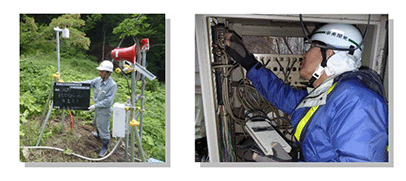
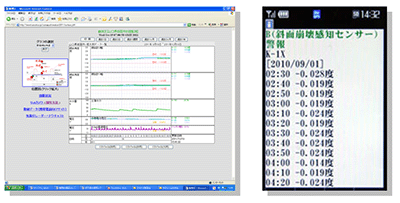
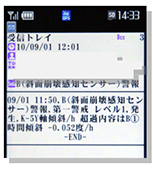

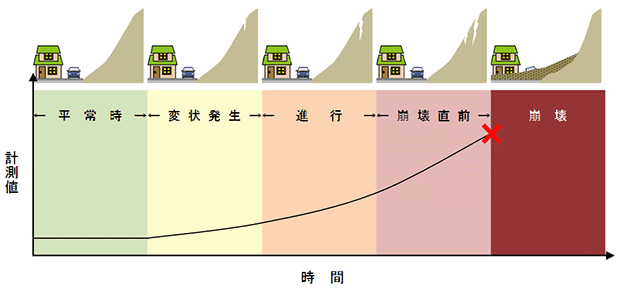

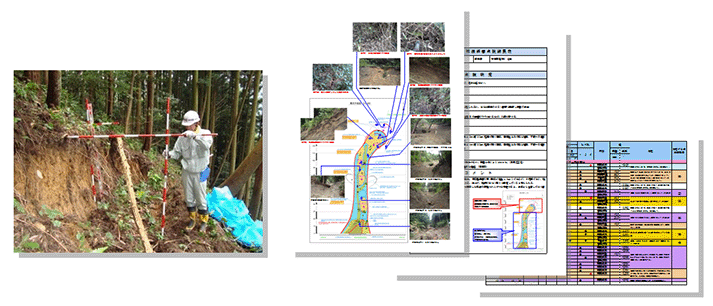
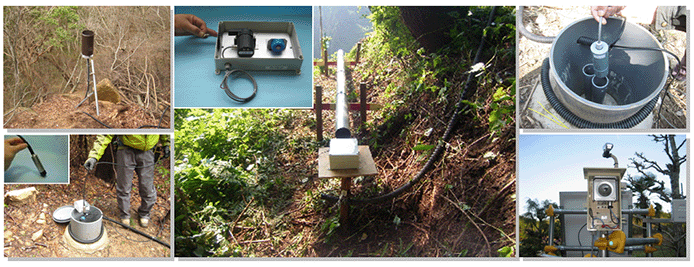
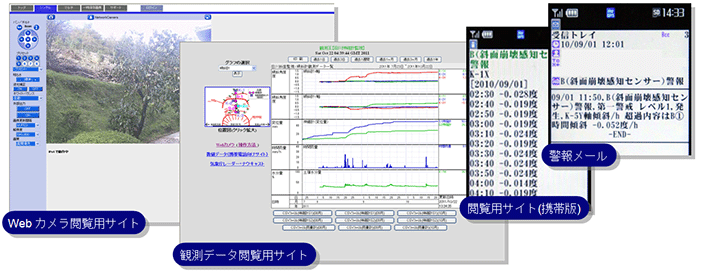
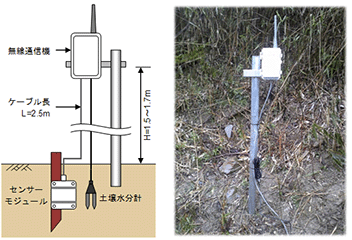
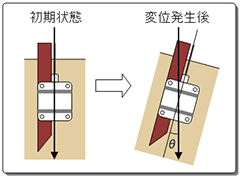
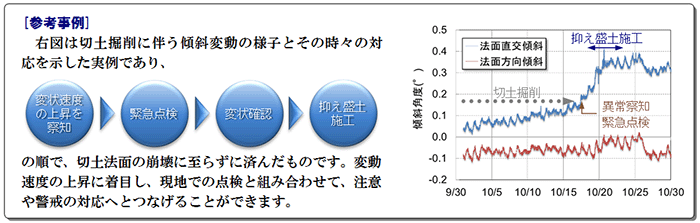
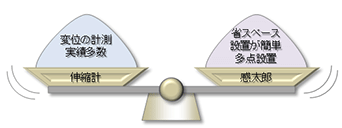

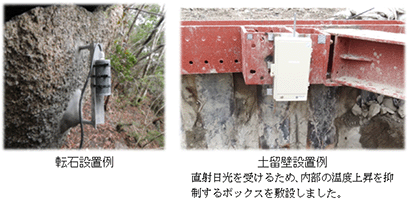
 直径25mmのロッド内部にセンサーユニットを組み込み
直径25mmのロッド内部にセンサーユニットを組み込み